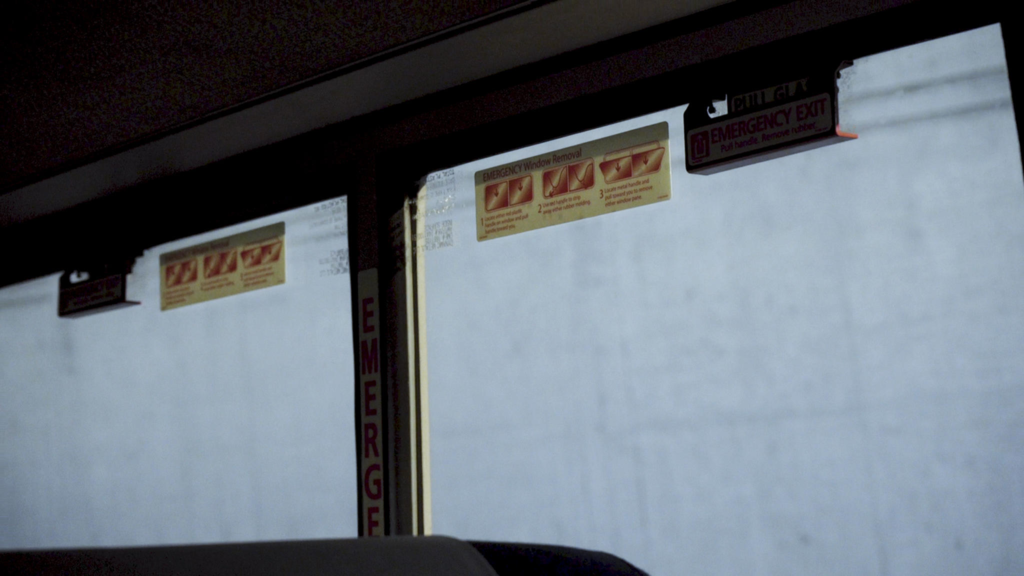日本人は無宗教な人種だとよく言われる。しかしそれは少し間違っているのではないかと自分は思う。個人的には、日本人はそれ以前に宗教という概念をそもそも理解していないのが実際のところでは?と思っている。それは宗教的な事柄があまりにも世俗化されすぎて(例えば初詣やクリスマスなど)実体を失っているゆえだ。だからアメリカ映画におけるキリスト教的要素など宗教に関しては理解が難しいのだ。今回紹介するアルバニア映画、Robert Budina監督作“A Shelter Among the Clouds”も日本人からすれば難しいかもしれない。だが宗教という概念の複雑さ、その一端へ確かに触れることができる一作でもある。
今作の主人公は中年男性のベンシック(Arben Bajraktaraj)、彼はアルバニアの山奥で羊飼いとして暮らしている。そんな仕事の傍ら、寝たきりの父親を孤独に介護する日々をも送っていた。敬虔なイスラム教徒である彼の心の拠り所はアラーであり、毎日欠かさずに祈りを捧げ続けている。
まず監督は広大な自然の中に根づいている日常を丹念に描き出していく。崇高さを帯びた山々に囲まれながらベンシックは羊などの動物たちを育てている。その合間には大地や風の存在を全身で感じとりながら祈りを捧げていく。そういった風景を撮影監督のMarius Panduruは端正に切り取っていくのだ。そこには静かなる情熱が宿り、観る者に畏敬の念を抱かせるだろう。
ある日、ベンシックは足しげく通っていたモスクの壁に謎のほころびを見つける。修復のためにやってきた外部の調査員が言うには、壁の奥に見えるのは聖母マリアの壁画であり、つまりこのモスクは昔カトリック教徒が通う教会であったことが判明したのである。
小さなこの村では宗教が共生してきた歴史がある。イスラム教とキリスト教がデリケートな平衡感覚の上で持ちつ持たれつ生きてきたのだ。しかしモスクが教会だと判明した後から、その均衡が崩れ始める。ベンシック自身はこのモスクをキリスト教徒にも解放すべきであると主張するのだが、イスラム教徒たちはそれに反対し、不満が噴出し始める。
ベンシックの人生自体も、この宗教の複雑な対立を反映していると言えるかもしれない。亡き母は敬虔なキリスト教徒であったのだが、父は共産主義者であり宗教を忌み嫌っている無神論者でもある。しかしベンシックはどちらの宗教観も受け継ぐことなきイスラム教を信仰することとなる。それについて父は常に文句を言いながらも、外の声には耳も貸さず、彼は厳格にアラーに祈りを捧げ続ける。
物語において中心となるのは、そんなベンシックの信仰が様々な側面から試される姿だ。彼はリリエ(Suela Bako)という調査員の女性と出会い、信仰について様々な対話を重ねながら、微妙な関係性に陥っていく。だが帰省してきたきょうだいたちとは仲違いをし、どうにも苦悩が募る。追い打ちをかけるように、介護していた父親の容態が急に悪くなり危篤状態に陥ってしまう。そうしてベンシックは“自分はどうすればいいのか?” “何をすればいいのか?”を常に問われることになる。
そして彼の宗教的な苦悩が崇高なる雰囲気で以て描かれていく。物語には信仰を震わされる時に、自分の存在それ自体をも震わされてしまうという実存的な震えが濃厚にある。そんな中で小さな祈りが大自然の中に響き渡る様はこの苦悩がいかに切実かを指し示していると言えるだろう。この果てに、ベンシックが1つの選択を行うことになる。
今作は宗教的な混迷が巻き起こす試練に直面する男の姿を描き出した作品だ。この映画のニュアンスを深くまで理解するのは、日本人には難しいかもしれない。しかし宗教という大きな概念をひとりの男の小さな視点から描き出すという作品ゆえに、宗教というものに触れるにはいい出発点でもあるかもしれない。
Roberto Budinaはアルバニアを拠点とする映画作家だ。まず演劇を学んだ後、戯曲の執筆や舞台の演出を多く手掛ける。2001年にはSabina Kodraと共に製作会社ERAFILMを設立し、ここから映画製作に乗り出す。日本でも上映されたラウラ・ビスプリ監督の「処女の誓い」の製作も務めていた。映画作家としては2012年の初長編である"Agon"を完成させる。よりよい未来のためにギリシャへと移住した兄弟の姿を追った作品で、2014年のオスカー外国語賞アルバニア代表にも選ばれた。そして2018年には今作を完成させ、タリン・ブラックナイツ映画祭で好評を博すことになった。ということでBudina監督の今後に期待。

私の好きな監督・俳優シリーズ
その321 Katherine Jerkovic&"Las Rutas en febrero"/私の故郷、ウルグアイ
その322 Adrian Panek&"Wilkołak"/ポーランド、過去に蟠るナチスの傷痕
その323 Olga Korotko&"Bad Bad Winter"/カザフスタン、持てる者と持たざる者
その324 Meryem Benm'Barek&"Sofia"/命は生まれ、人生は壊れゆく
その325 Teona Strugar Mitevska&"When the Day Had No Name"/マケドニア、青春は虚無に消えて
その326 Suba Sivakumaran&“House of the Fathers”/スリランカ、過去は決して死なない
その327 Blerta Zeqiri&"Martesa"/コソボ、過去の傷痕に眠る愛
その328 Csuja László&"Virágvölgy"/無邪気さから、いま羽ばたく時
その329 Agustina Comedi&"El silencio es un cuerpo que cae"/静寂とは落ちてゆく肉体
その330 Gabi Virginia Șarga&"Să nu ucizi"/ルーマニア、医療腐敗のその奥へ
その331 Katharina Mückstein&"L'animale"/オーストリア、恋が花を咲かせる頃
その332 Simona Kostova&"Dreissig"/30歳、求めているものは何?
その333 Ena Sendijarević&"Take Me Somewhere Nice"/私をどこか素敵なところへ連れてって
その334 Miko Revereza&"No Data Plan"/フィリピン、そしてアメリカ
その335 Marius Olteanu&"Monștri"/ルーマニア、この国で生きるということ
その336 Federico Atehortúa Arteaga&"Pirotecnia"/コロンビア、忌まわしき過去の傷